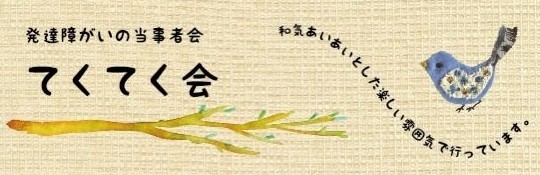お皿の物語、その二
皆様、前回のお話から「習慣を変えてゆけばいい」ということに気付きましたか。
今日はその続き、私がお皿を洗えるようになった過程について書きたいと思います!
どうして今までお皿をうまく洗えなかったのでしょう。
考えてみたら、いくつかの理由に気付きました。
1.台所の流しが非常に狭く行動する場所があまりない
2.聴覚優位のため、視覚を利用して判断する力が非常に弱い。お皿が「山」 に なったことに気づけない
3.疲れきっているので、お皿まで洗う元気がない
4.直ぐに洗わないので、汚れがしつこく、洗ってもすっきりときれいにならない
5.気づいた時に洗うのがとにかく難しい。とにかく出来ない
ご存じの通り、発達障害があります。出来ると出来ないことの差が非常に大きいです。てくてく会では、出来ると出来ないことを三つの種類で分けています。
1.本当に出来ないこと。どんな方法でも本当に無理。
「本当に無理なことはやらなくて良いのです。出来る人に任せてください」
2.苦手です。けれども、あらゆる「対策」をすれば、出来るかもしれません。
「苦手なことなら、最低限のことをやりましょう」
3.得意なこと。
「得意であれば、だんだん伸ばしましょう。集中すれば少しずつ伸びるでしょう」
私的に、お皿洗いは2番の「苦手」なのだと気づきました。本当に無理なのではなく、難しいのです。それでは、何を変えたのでしょうか。11月のある日、「山」から「お皿」に感覚を変えたのです。
もちろん、本当に「山」だと思っていたわけではありません。けれども、それまでは1番の「とにかく無理」だと感じていたので、そのように扱っていました。
状況を改善することで、できるようになってきた過程を紹介します! まず私は、毎日7枚のお皿を洗うことを心がけました。7枚洗ってもまだすごく残りました。けれども、洗うことが習慣になり、毎日流しを見ることを意識しました。7枚洗ったら、簡単に記録を書きました。このようにして10日間が経ちました。
11日目から、「食事をしてから、直ぐに3枚を洗う。」ことにしました。そうすれば1日で9枚になりますよね。まだ残っています。けれども、一切できていない状態から「毎日、9枚洗う」ようになりましたから、気持的には全然違います。
これを続けて翌週は「食事してから、直ぐに4枚を洗う」ことにしました。そうすれば1日で12枚を洗えます。
こうして一週間ごとに洗う数が増えて、洗うことが当たり前になっていきました。すごく難しいことではなく、毎日の流れの一部分になったのです。
まだまだ改善中ですが、お皿の状態が11月と比べたら、全然違います。
もしあなたに変えたい習慣があるならば、小さな一歩から始めませんか。今年こそ、何を改善したいですか。